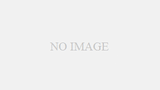共働きパパの育休1年体験談|メリット・デメリットと学んだこと
はじめに
今回は一年間(12か月)の育休体験をもとに、共働きパパが1年の育休を取るメリット・デメリット、そして実際に学んだこと をお伝えします。
これから育休を検討している方、現在育休中の方の参考になれば嬉しいです。
男性育休の現状
厚生労働省の「令和6年度 雇用均等基本調査」によれば、男性の育休取得率は 40.5% と過去最高を記録しています。
しかし、実際の取得期間は 平均約46.5日(約1か月半) にとどまっており、依然として短いのが現状です。
👉 出典:厚生労働省「令和6年度 雇用均等基本調査」
赤ちゃんの生活リズムが安定するのは生後3〜4か月以降であり、妻の体力回復や夫婦の家事・育児分担を考えると 1か月半では不十分 だと強く感じました。
実際に私が1年の育休を経験してみて、半年以上の期間を取ることで子育ての大変さと喜びの両方をしっかりと体験できたと実感しています。
育休1年を取るメリット
1. 子どもの成長を間近で見守れる
赤ちゃんの首すわり、寝返り、はいはい、つかまり立ち。
1年間一緒にいることで、毎日の小さな成長を逃さず見守れました。
これはお金には代えられない経験です。
2. 妻をしっかりサポートできる
産後は妻の体調が安定せず、心身の負担も大きい時期。
私が家事と育児を分担することで、妻の回復がスムーズになり、夫婦の関係性も良くなりました。
3. 家事スキルが格段に上がる
料理、掃除、洗濯、買い物。すべてを日常的にやるようになり、「生活力」 が一気に向上。
育休後の生活にも大きなプラスとなりました。
4. 子どもとの絆が深まる
一緒に過ごす時間が長いことで、子どもが自然と私に懐くようになりました。
「パパじゃなきゃダメ」と言われた瞬間は本当に嬉しかったです。
育休1年を取るデメリット
1. 収入が減る
育児休業給付金は最初の6か月が67%、7か月目以降は50%に減ります。
共働きでも収入はかなり減少し、貯金の取り崩しや節約は必須でした。
2. 住民税やふるさと納税に注意
収入が減ると控除枠も減少し、ふるさと納税額も大幅に減ります。
また、住民税は自分で納付する必要があり、3か月ごとに大きな額を払うのは正直大変でした。
3. キャリアへの不安
1年間現場を離れることで、復帰後のキャリアに影響があるのではと不安もありました。
ただ実際には、会社も制度を理解しサポートしてくれたため、大きな問題はありませんでした。
実際に学んだこと
- お金の準備は必須
育休に入る前に、半年〜1年分の生活費を貯めておくと安心です。 - 夫婦で役割分担を明確にする
家事・育児を「できる方がやる」ではなく、しっかり分担を決めておくとストレスが減ります。 - 時間の使い方を意識する
24時間子どもと一緒にいる生活は想像以上にハード。
「休む時間」「自分の時間」も確保することが大切です。
まとめ|共働きパパだからこそ育休は価値がある
1年間の育休を通して感じたのは、共働き家庭にとって育休は「休み」ではなく「家族のための投資」 だということ。
- 収入は減るけれど、子どもの成長を近くで見守れる
- 妻との関係が深まり、家庭の基盤が強くなる
- 自分自身の生活力も向上する
👉 これから育休を検討している新米パパへ。
6か月でも1年でも、できる範囲で育休を取ることを強くおすすめします。
きっとあなたと家族にとって、一生の財産になるはずです。